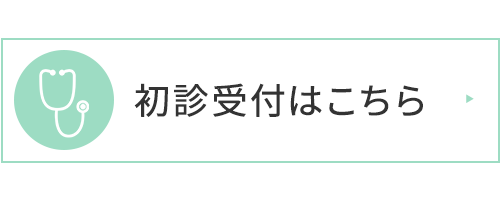病気について

生活習慣病ってどんな病気?
1996年までは「成人病」と呼ばれていました。食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群とされています。さらに最近は遺伝など生まれつきの要素もあり、 「必ずしも本人の不適切な生活習慣に帰するとは限らないため生活習慣病という表現は適切ではない」という意見もあります。
また、従来は治療管理に難渋していた生まれつきリスクの高い方であっても、近年の疫学データや新薬によって病状を管理しやすくなってきていますので、自身の病態に早い段階で関心を持って取り組んでいただくことが重要です。
病院勤務時代には内科専門医として長年の高血圧症や糖尿病の結果として生じた腎不全の患者さんや、心臓病や脳血管障害の既往のあるリスクの高い患者さんを20年以上診療してきました。このため「高血圧症」「糖尿病」「高脂血症」などの治療は高度で特別な医療ではありませんが重要なことと考えています。さらに、近年は禁煙や減酒についても補助薬の併用などで取り組みやすくなってきているので、気軽にご相談ください。
高血圧症

高血圧症は多くの場合、自覚症状がほとんどないままに進行します。しかし放置しておくと、動脈硬化が進行して血栓症(脳梗塞、心筋梗塞)や血管の破綻による大出血(脳出血、大動解離・破裂)、臓器血流の低下(高血圧や弁膜症による心不全、腎不全、末梢動脈疾患)など命に関わる疾患を、人生の後半において引き起こします。
それぞれの皆さんの状態にもよりますが、おおむね血圧130/80mmHg以下になるように管理することが望ましいと考えられています。勤労世代の血圧上昇には精神的なストレス・運動不足やアルコールの摂りすぎはリスク要因になります。一方で高齢者の一部の方はあまり下げすぎないなどの配慮も必要です。また、他の疾患で服用している薬剤による血圧上昇や、睡眠時無呼吸の治療や外科手術を行うことで完治する高血圧症もあり、高血圧症はありふれてはいますが奥の深い診療でもあります。
私自身が日本高血圧学会の専門医として関心のある分野でありますので、病態に応じて適切な降圧目標を設定し最小限の投薬での治療を心掛けます。
糖尿病

私たちが摂取した栄養は、「ブドウ糖」まで分解され体を動かすエネルギーとして使われます。そしてこの糖の代謝に関わるものとして、膵臓から分泌されるホルモンである「インスリン」があります。インスリンはブドウ糖をエネルギー源として筋肉や肝臓の細胞に取り込む役割を果たすとともに、ブドウ糖が血中に残りすぎないように調整します。
インスリンの分泌量が低下していたり、インスリンに対する細胞の反応が弱かったりすると、糖が血液内に残ることになり高血糖状態を生じ、長期的には細い血管の障害を引き起こし末梢神経症、網膜症、腎症などにより感覚障害、失明、人工透析を招き日常生活の質を低下させます。さらに高血圧症や脂質異常症もあると、足の壊疽、狭心症、脳梗塞など命に係わる合併症を併発しやすくなるので、糖尿病もまた早期の発見と治療が必要です。
糖尿病も発症しやすい方/そうでない方、同じコントロールでも臓器合併症を起こしやすい方/そうでない方がおられ、単純な病態ではありません。また、糖尿病においても治療成績の優れた新薬が登場し大きく変わっていますので管理が難しいケースは専門医のご意見を伺いながら、標準治療を実践して参ります。
脂質異常症

脂質異常症とは、中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常がある状態です。高脂血症状態が続くと、血管壁に余分な脂がへばりつきます(動脈硬化プラーク)。プラークは、血液の流れを阻害し、細胞に栄養と酸素がいきわたることを邪魔します。その結果、狭心症や脳血管障害、下肢の血行障害など動脈硬化症をもたらします。プラークの突然の破綻は急激な血栓症を起こすため心臓の血管で生じると心筋梗塞、頸部の血管で生じると脳梗塞となります。
脂質異常は肥満の方や大酒飲みの方に多く、生活スタイルの見直しが重要です。その一方で、いわゆる悪玉とされるLDLコレステロールは肝臓のコレステロール合成酵素の生まれつきの働きで差があり、痩せていても高い方がいらっしゃいますし、生活習慣だけでは改善できないこともあります(巷に言う卵の黄身を過剰に制限する必要はありません)。LDLが高いだけではすぐの介入は不要なのですが、すでに複数の生活習慣病や動脈硬化症のある方には厳格な管理が必要であり、内服治療をお勧めします。
非感染性疾患 NCDs(Non-communicable diseases)という考え方

2013年に世界保健機構(WHO)が定義した疾患群であり、循環器疾患・がん(※)・慢性呼吸器疾患・糖尿病などの非感染性疾患の総称です。世界の死因の7割を占めるとされており、いわゆる生活習慣病の延長線上にある合併症の多くがこれに含まれます。若年者の死亡原因となるがんやメンタルヘルスなども含まれています。
2019年以降はコロナウィルス感染が最大の脅威となっていましたが、WHOはNCDsによる死亡者の減少を現在も大きな課題としており、我が国の医療行政にも大きな影響を与えています。高度医療機関での急性期治療と合わせて、患者さんご本人+かかりつけ医による日々の一次予防(発症予防)、二次予防(再発予防)が重要となります。
※子宮頸がんやB型肝炎ウィルスによる肝がんはNCDsではありませんがワクチンで予防可能な感染性疾患であるといえます。